こんにちは!ママ防災士のヌマです。
我が家には7歳と4歳の娘がいます。
娘たちは工作が大好き!

そんなある日、次女にピッタリな、しかも防災教育要素のあるペーパークラフトが付録になった雑誌を発見!
小学館の知育学習雑誌「幼稚園」2024年10・11月の付録「おやこで!AEDたいけんセット」!
\付録AEDの音声大公開!/
大好評発売中!『幼稚園』10・11月号の
付録AEDの音声が聞ける動画です🔊本物のAEDも、ふたを開くと音声が流れて
使い方を教えてくれます。ぜひ、音声ガイドにあわせて
操作を練習してみてください✨ pic.twitter.com/VTOIqw7Y6t— 小学館『幼稚園』編集部 (@youchien_hensyu) September 12, 2024
ママ防災士として日頃から熱心に子どもたちへの防災教育に取り組んでいる!
…ということは全くないのですが、これは楽しく防災的なものに触れるチャンス!と思い購入しました。

あわせてチェック
この記事の目次
AEDをペーパークラフトで作ったら、子どもたちの意識が変わった?!
.jpg)
「幼稚園」を購入してからすぐに、次女と2人で過ごすお休みの日があったので、いざ一緒に工作開始!
一度でも作ったことがある方はご存知かもしれませんが、「幼稚園」の付録ペーパークラフトはかなり複雑な作りになっております。

工作大好き4歳(と母)、頑張ってAEDを作る
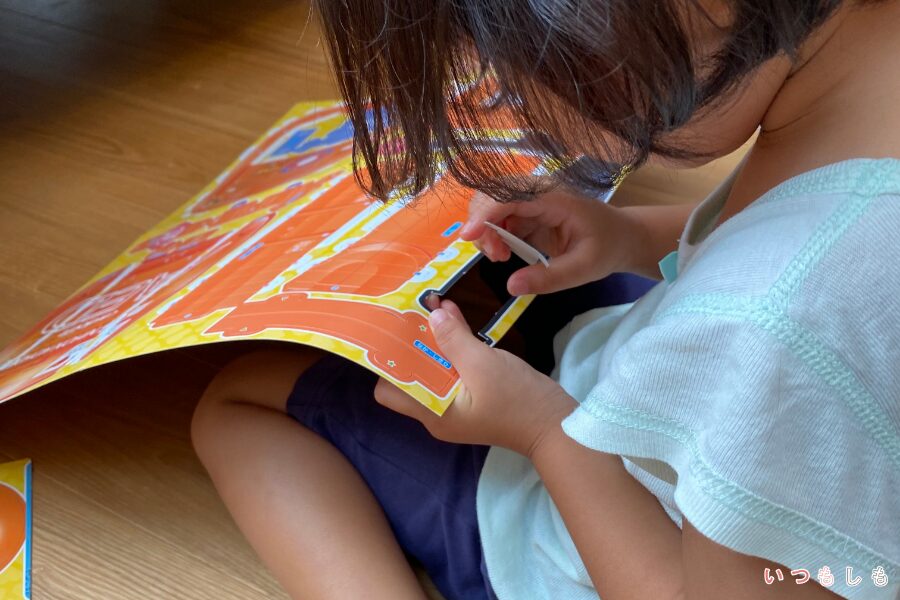
我が家の工作大好き4歳はペーパークラフトのパーツを台紙から外す作業がお気に召したようで、ひたすらプチプチプチ…。
その傍で作り方解説ページを凝視しながらブツブツと独り言を発する母。
黙々とパーツを取り外し、山折り谷折りを施す次女、そのパーツを受け取り組み立てる母。
しかし必要なパーツがめちゃくちゃ多いので、

といいかげん飽きてきた様子の4歳児。

と何とか鼓舞しながら正確に、かつ素早く、パーツを接続していきます。

ここで

とならないところ、さすが工作好き!
完成したら、使ってみる!
いつ次女に見捨てられるかとヒヤヒヤしながらも、何とか興味を繋ぎ止めた状態で、やっとやっと完成!
.jpg)
ボタンを押すと本物と同じ音声ガイダンスが流れます。
その緊迫感に大人はちょっとドキドキ。
倒れた人を模したペーパーには、ネックレスのパーツまでついています。
これはきっと、電気ショック時の感電を防ぐために金属のアクセサリーを身につけている場合は取り外そうね、という話をするためのもの。

胸骨圧迫をやってみせましたが、4歳児、ポカンとしておりました。
まだ年少には難しかったか…と思っていたのですが、数日後、ある光景を目にすることに…。
ペーパークラフトAEDの驚くべき効果
ある日、お気に入りのぬいぐるみに胸骨圧迫を施しながらAEDを使う次女の姿が(笑)。

おかげで「えーいーでぃー」という単語を覚え、病院やドラッグストアなどでAEDを見つけると

といえるほどAEDを認識できるようになりました。
完成したペーパーAEDで次女と一緒に遊んでいた小1の長女も、AEDの文字列はしっかり覚えたようで

と教えてくれるようになり、なんだか誇らしい気持ちになりました。
遊びだけで終わらせないッ

とほっこりしていた私に、ふと不安がよぎりました。

防災士試験受験のために、応急手当て講習を受けた際に、AEDの使い方は一通り学びました。
でも、もちろん普段は使わないので(使う機会がないのは喜ばしいことなのですが)それはもう日々刻々と記憶が薄れていきます。

せっかくだから子どもたちの興味がAEDに向いている今、家族みんなで受けれないかな?と思い立ち、子連れでAEDの使い方が学べる講習会を探しました。
子どもと受けられる救命講習ってあるの?


ふらりと立ち寄った地域のお祭りや防災イベントなどの消防関連のブーステントには、練習用の人形でAEDと応急手当てが体験できるコーナーがありました。
当時の我が家の子どもたちはというと、不気味に横たわる上半身のみの人形たちに怯み、そのブースを遠くから見つめるだけ。
「やってみる?」と聞くと、父の後ろに隠れ、黙って首を横に振るのでした(笑)。
消防署で「子連れ参加OK」の講習会を発見!
近々そういった体験ブースがありそうな地域イベントの開催予定もなかったため、検索してみることに。
「〇〇市(住んでいる自治体) + 救命講習 + 子連れ」で検索すると、消防署で開催されている定期講習のページがヒットしました。
しかも「小さな子どもの同伴可」と書いてある講習があるではないですか!
check
私の住んでいる自治体では、救命講習が「受講」できるのは小学4年生から。
それより小さい子どもは、同伴は可能ですが、受講修了証などはもらえません。
お住まいの自治体で実施されているかどうか、ぜひ一度検索してみてください。
年少と小1の子どもたちが2時間もある講習に耐えられるはずがないので、小児・乳児に対する心肺蘇生とAEDの取扱いが学べる「救命入門コース(90分)」に目をつけました(90分も十分に長い!)。

私が前回受講した講習会は成人を対象とした普通救命講習だったので、小児を対象とした救命をぜひ学んでみたい!と思いスケジュールをチェック。

防災に興味がない家族を説得!






最難関(?)の渋る夫も


などと言い、なんとかかんとか説得した後、消防署へ電話し、無事に申し込みを完了しました。
いざ、講習会へ!
.jpg)
講習会が開催される消防署は、同じ市内と言っても高速道路で行くような距離にあったので、ちょっとしたお出かけ気分で行けたらいいなぁと思っていたのですが、まず、言うことをすんなり聞いてくれないお年頃の4歳児。
車に乗せるだけと思いきや、一筋縄では出発できません。

(その日ポケモンセンターが移転工事のため営業していないことに気付いたのは、また別のお話…)
消防署、行くだけで防災意識アップする!?
消防署近くのコインパーキングに車を停めて歩いていると、消防署の前に公衆電話を発見!
ご近所では全然見かけない公衆電話。せっかくなので子どもに触ってもらいました。

子ども向け公衆電話の使い方については、こちらの記事を参考にしてみてください。
-
記事タイトル|いつもしも with Kids
公衆電話(こうしゅうでんわ)とは、だれでも使(つか)える電話(でんわ)のことです。 駅(えき)やお店(みせ)、道(みち)などに置(お)いてあるのを見(み)…
続きを見る
そして消防署の外では、ちょうどレスキューの訓練中。
高い壁をするすると登っていく隊員の方々。


ちょうど近くを通りかかった小さな男の子とそのパパママも、訓練の様子を見学していました。
中に入ると、通路の向こう側に、ズラーっと並ぶ防火服たち。

ちょっと興奮気味に長女に話す母(私)。

会場の様子はこんな感じ
.jpg)
講習が開催されたのは消防署の2階にある大きなセミナールーム。

練習用に使う小学生くらいと思われる幼児(上半身だけ)の人形と、オムツを履いた赤ちゃんの全身人形(子どもたちに何度もおむつのテープを剥がされていました)、それから訓練用のAEDが1人につき1セットずつ置かれていました。
定員10組の講習会だったので、部屋の半分のスペースは空いていて、とても広々。
案の定、我が家の子どもたちは途中から講習に飽き、優しい消防職員さんたちに気が緩み、会場内を駆け回りました。ごめんなさい…。
初めは説明資料を見ながら、消防職員さんたちの話を聞きます。
どんな時に起きる?「子どもの心停止」
講習では、心停止の主な原因として以下が挙げられていました。
子どもの心停止の主な原因
- 水の事故(溺水)
- 誤飲誤嚥による窒息
- けが(外傷)
- やけど
お風呂で溺れたり、窒息が原因で呼吸が止まると、酸素が足りなくなり、体内の各細胞でエネルギーが生み出されないため、心臓が活動できなくなり、やがて心停止に陥るそうです。
また、子どもは胸部が柔らかいため、強い衝撃を受けると「心臓振盪(しんぞうしんとう)」を起こしやすく、これによって心室細動(心臓がブルブルとけいれんする状態)が引き起こされ、心停止に至るそうです。
子ども自身が高いところから落下したり、ボールが強くぶつかったりした時に起こるとのことでした。
私が知らなかったのは「やけど」が原因の心停止です。
感電によるやけどのことを「電撃傷」といい、最悪の場合心停止を起こすことがあるそうで、電源プラグを口に入れたり、コンセントにヘアピンを突っ込んだりしてやけどを負う事故が実際に起こっているそうです。
子どもの心停止の原因は、大人が十分に注意をして予防することで、未然に防ぐことができるものも多いです。

改めて家の中の危険な箇所を見直すきっかけになりました。
反応がない人がいたら、まずは119!そしてAED!
ひとたび心臓と呼吸が止まると、そこからはまさに1分1秒の勝負です。
注意
「心停止」の状態になると、数秒で意識を失い、3分で脳をはじめとした身体中の細胞が死んでいってしまうそう。
119 番通報をして、救急車の到着を待っている間にも、どんどん救命できる確率が下がっていくのです。
より早く救命活動を開始することで、その人が生きられるかどうかが決まるため、何より「早い通報」「早い応急手当て」が大切と実感しました。
資料を見ながらの説明が終わると、次は実際に人形を使いながらの実技講習です。
いざ実技!
.jpg)
消防職員の方が見本を見せたあと、参加者の私たちも実際にやってみます。
全体の流れはこんな感じ。
応急手当ての流れ
- 反応の確認
- 助けを呼ぶ
- 呼吸の確認
- 胸骨圧迫30回
- 人工呼吸2回
- AED到着
- 電気ショック
- 4〜7の繰り返し

実際にもらったアドバイスと共に振り返ります。
1.安全の確保と反応の確認
- 倒れている人を見つけたら、周りの安全を確認
- 危険な場所で倒れている場合は、安全な場所へ移動を
- 両肩を強めに叩いて、反応の有無を確認
反応確認の時は、「強め」に「両肩」を叩いて呼びかけるのがポイントとのこと!
- 強く叩くのは、刺激を与えて反応があるかを確認するため。
- 両肩を叩くのは、片方が麻痺していて感覚がなかった時のため。

「大丈夫ですか!?」と突然人形に話しかける母に驚く子どもたち。
2.助けを呼び、周りに声をかける
- 反応がなければ、周りの人に声をかけて助けを呼ぶ
- 周りに誰もいない時は、自分で119へ電話
目の前にいる人を指を差して「あなた、119番してください!」「あなたはAEDを取ってきてください!」と言うのがポイント。

身につけているものや服の色を言ってよりわかりやすくするとさらに伝わりやすいです。
また、「救急車」ではなく「119番」としっかり番号を伝えることも、間違えて110番に電話してしまうことを防ぐために重要とのことでした。
周りに誰もおらず、自分1人しかいなくても、119番に電話すればオペレーターが電話口で指示してくれるので、ハンズフリーで話しながら応急手当てを続けます。
コラム
誰かが倒れた時、その場に居合わせた人のことを「バイスタンダー」というそうです。
バイスタンダーが複数いれば、119番に電話をしたり、AEDを取りに行ったりと、後に説明する胸骨圧迫を交代しながらスムーズに行うことができます。
このバイスタンダーになれる人が1人でも多く増えることで、多くの人の命が救われると考えられています。
3.呼吸の確認
- 「普段通りの呼吸」かどうかを確認
一昔前の応急手当てでは、口元に自分の頬を近づけて、呼気が当たるかどうかを確認する方法もありましたが、現在は「胸」と「お腹」の動きを見て「普段どおり」の呼吸があるかを10秒以内でチェックする方法が確実とされています。
心肺停止状態の人は、ゲップやしゃっくりのような呼吸をしたりすることがあり(死戦期呼吸というそうです)、口元に顔を近づけて確認すると、頬に呼気があたるから息をしている!と勘違いすることがあるそう。
「普段通りの呼吸」をしていたら、胸やお腹はゆっくりと上下に動きます。
その動きを思い出し、確認することが大切。
非常時は頭の中で数を数えると途中でわからなくなることがあるので、10秒は「いち、に、さん、しー、ご…」と口に出して数えるのが確実とのこと。

よくわからなくて迷ったら、「呼吸なし!」と判断して、胸骨圧迫へ。
4.胸骨圧迫
- 呼吸なしと判断した場合、30回の胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始
- 肘を真っ直ぐに伸ばし、手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸が約5cm沈むように強く圧迫
- 胸の「真ん中」を強く・速く・絶え間なく圧迫
胸骨圧迫で私が驚いたのは心臓の位置の話です。
人間を正面から見て縦半分に分けた時、心臓は中心より少し左にあると思っていました。
でも実際は身体の中心にあるんだそうです。なので胸骨圧迫する位置は胸の真ん中。
心拍が左側から聞こえるのは、心臓の形が左側に曲がっているから、とのこと。
.jpg)
日本医師会「救急蘇生法」より引用
また、胸骨圧迫のポイントを教わりました。
胸骨圧迫のポイント
- AEDが到着するまで、到着してもそのまま胸骨圧迫を継続すること(AEDが到着すると安心して手が止まりそうですが、そのまま続けることが何よりも大切だそうです)
- できるだけ硬い床の上で行うこと(ソファやベッドの上などの柔らかい場所では、圧迫の力が逃げて有効にならないことがあるため)
- 正しい姿勢で行うこと(圧迫の姿勢や位置などをときどき確認しながら続ける)
- 圧迫の手は離さず、元の位置まできちんと戻すこと
- 大きな声で30回数えること
- 肋骨が折れてもやめないこと

圧迫するテンポは、1分間に100~120回で、絶え間なく続けます。
胸骨圧迫は体力勝負です。同じリズムで 30回、60回、90回…と続けていると、とても疲れてきます。
バイスタンダーが2人以上いる場合には、胸骨圧迫は1~2分を目安に交代します。
胸骨圧迫のリズム、強さのイメージは、こちらのポストを参考にしてみてください。
ドクターカーにはこの機械的胸骨圧迫装置を積んでいます。
胸骨圧迫(いわゆる心臓マッサージ)は適切なリズム、深さで行うことが大切なのですが、実際に人力で行うとかなりの体力を使いますし、それを行うために人手が割かれてしまいます。
(続)pic.twitter.com/FgqnJ1KUIy— 科学大ER(東京科学大学病院 救命救急センター) (@ScienceTokyo_ER) July 16, 2025
乳幼児の胸骨圧迫は、指がめちゃくちゃ痛い!
乳児の胸骨圧迫では2本の指を立てて胸部を押します。
幼児も基本的には成人と同じ方法です。胸骨を押し込む目安は、横から見た時に身体の1/3が沈むくらい。
.jpg)
日本医師会「救急蘇生法」より引用

成人や幼児の胸骨圧迫では、自分の体重を手の付け根に乗せますが、乳児の場合は指の腹の部分に自分の体重を乗せます。
30回も圧迫を繰り返していると、指が折れそうなくらい痛い!

そして乳幼児は正しく力をかけないと、すぐに肋骨が折れてしまうそうです。
もちろん折れたとしても、胸骨圧迫をやめてはいけません。

5.人工呼吸
- 気道確保
- 人工呼吸は原則行わない
新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延してから、人工呼吸のあり方は大きく変わりました。
消防署の職員さんによると、現在でも、成人の場合は「なんらかのウイルスに感染しているもの」と考え、人工呼吸はしない方針だそうです。
ただ、人工呼吸をしなくても空気の通り道である「気道」の確保が必要です。気道確保をしなかった場合、舌が喉に落ち込んで気道を塞いでしまい、息が出てきません。
気道確保の方法
- 人差し指と中指を傷病者のあご先に当てる
- もう片方の手のひらを額に当てる
- あご先を持ち上げながら、額を後方に押し下げる
乳幼児は人工呼吸が推奨されている
乳幼児に関しては、窒息や誤嚥など、呼吸が止まったことが原因の心停止が多いため、可能な限り人工呼吸をしてあげてください、とのことでした。
実際に人工呼吸の実技練習はしませんでしたが、乳幼児に人工呼吸をする時の注意点として、
注意
- 肺が小さいため、息を強く吹き込みすぎると、空気が胃の方に入ってしまう恐れがある
- 軽く胸が上がるくらいの強さで優しく吹き込みましょう
と教わりました。
6.AEDが到着!
-1.jpg)
- 胸骨圧迫の継続
- 作業分担の確認
ここでやっとAEDの出番ですが、胸骨圧迫はやめず、継続したまま!
胸骨圧迫を続けながらAEDを運んできてくれた人に「あなたは、AEDを使えますか?」と聞きます。
相手がAEDを使えないと答えた場合は、胸骨圧迫を交代して、自分でAEDを使います。
AEDは音声ガイダンスにきちんと従えば使うことができますので、一度でも練習したことがあれば、恐れずに「使えます!」と言いましょう!
7.電気ショック
- 音声ガイダンスに従って電気ショックを実施
- 人が触れていないことを確認
音声ガイダンスに従って、正しくパッドを貼ると、AEDは心電図の解析を行います。
パッドを貼る正しい位置についてはこちらをご覧ください。
解析の結果、必要があれば、「電気ショックが必要です。体に触れないでください」というガイダンスが流れます(AEDの機種によってガイダンスのセリフは違います)。

私よし!
と倒れている人の体に誰も触れていないことを目視し、声に出して確認した後、ショックボタンを押して電気ショックを行います(カウントダウンによって電気ショックが行われるものもあります)。
AEDのボタン、子どもも押せる?
お目当て(?)のAEDの操作がやっと始まるという時、子どもたちは部屋の向こうのほうで、消防職員さんと何やら楽しげに話をしておりました(本当にありがとうございました)。

と呼び寄せます。
講習で使用したAEDは、開けると自動的に電源が入り、ガイダンスが流れるというもの。

パッドも貼りたい、ボタンも押したい、とにかく触りたい子どもたち。
きっと本番はこうはいきませんが、練習なので、電極パッドを一緒に人形に貼ります。
「電気ショックを行います、離れてください」
のガイダンスに合わせて、子どもたちに

と言い、電気ショックのボタンを一緒にPUSH!
ボタン自体は、子どもの力でも簡単に押すことができました。
そのあとはまた、呼吸の確認、胸骨圧迫、AEDでスキャンして必要であれば電気ショック、の流れを救急隊員が到着するまで続けます。
クマちゃんキーでAEDを小児モードにチェンジ!
AEDには未就学児(小児)用モードがあるものや、小児用パッドがあるものがあります。
私が参加した講習では、クマちゃんの形をした黄色いプラスチックの鍵を差し込むとAEDから「小児モードです」というガイダンスが流れ、モードが切り替わります。
こんな「小児用キー」を差し込むようなAEDがあるとは知りませんでした。これ知らないと、ついそのまま成人モードで使うか、小児用パッドを探しちゃうと思うなぁ。 pic.twitter.com/AX2vh2jxiL
— 遠藤登 @ 保育の安全×保育防災 (@NurseryOnline) January 30, 2019

コラム
※JRC蘇生ガイドライン2020に従い、これまでの「小児モード」「成人モード」の呼称は、「未就学児モード」「小学生~大人モード」へと、それぞれ変更がなされました。
まだ旧名称のAEDも設置されているため、
「小児」と書かれているものは「 未就学児」
「成人」と書かれているものは「 小学生から大人」
を意味すると考えてくださいと教わりました。

ショックが強くて心筋にダメージを与える可能性もありますが、効果が足りないよりは命を救える確率が上がるとのことでした。
8.心肺蘇生を繰り返す
- 電気ショック後の反応を確認
- (反応がなければ)胸骨圧迫再開
- 救急隊員の到着まで心配蘇生を継続
AEDによる心電図の解析は2分おきに自動的に行われるので、音声ガイダンスが再び流れるまでは心肺蘇生を続け、救急隊員が到着するまで応急手当ての流れを繰り返し続けます。

気道異物の除去
講習では、誤嚥・誤飲が原因で、気道に異物が詰まってしまった時の対処方法も教えていただけました。
一番身近な心停止の原因を考えた時、私がまず思い浮かべたのは「窒息」でした。
おもちゃを誤って口に入れてしまった時、プチトマトやマスカットなど丸いものが喉に詰まってしまった時などです。

後ろから背中を叩く、背部叩打法

喉に何か詰まった時は、まずはこの方法を優先して行います。
手のひらの根元(胸骨圧迫の時に使う部分)を、子どもの背中の左右の肩甲骨の間あたりに目掛けて、何度も強く叩きます。
これも人形で練習しましたが、結構強めに叩くので、実際にやる時には勇気が必要だなと感じました。
小さい赤ちゃんに対して行う時は、椅子などに座り、腕を太ももの上に固定します。赤ちゃんの顎と首のあたりを手で支え、腕にうつ伏せに寝かせた状態で背中を叩きます。
小さな赤ちゃんや妊婦さんは、次に紹介する腹部突き上げ法が使えないため、できるのはこの背部叩打法のみです。
お腹をぐっと突き上げる、腹部突き上げ法
背部叩打法では喉に詰まったものが出てこない場合、幼児以上であればこちらの腹部突き上げ法を行います。
- 子どもの後ろ側から、お腹に手を回す
- 片方の手でおへその位置を確認して、もう片方の手をグーの形にし、親指側をおへその上のほう、みぞおちより下に当てる
- おへその位置を確認した方の手で、グーの手を上から握って、上の方に向かって素早く圧迫するように突き上げる
腹部突き上げ法は、内臓を傷める可能性があるそうで、実施した場合は救急隊員に伝えるか、病院を受診する必要があります。
子どもの背部叩打法や腹部突き上げ法について、小児科医による図説も参考にしてみてくださいね。
子どもの事故予防に注目が集まっています。
のどにモノが詰まった!対処方法はこちら。心肺蘇生も。
資料はコンビニからシールで出せます。冷蔵庫等に貼るのもお勧め。実演の動画QRコード(東京消防庁)付き。
コンビニのマルチコピー機からの出力方法↓https://t.co/Ph2s23pDMZ
ツリーに動画も。 pic.twitter.com/xzK9C4ni4V— 教えてドクター佐久@無料アプリ配信中♪ (@oshietedoctor) September 29, 2022
救命講習が無事に終了!
子どもたちにとっては、とても長い90分の入門コースが無事終わりました。
途中で「まだ〜〜??」と言い始めた子どもたちに内心ヒヤヒヤしながらの参加となりましたが、優しい消防職員さんたちにたくさん相手をしてもらい、ポスターや組み立て式プルバックカーなどのお土産ももらって、撮影ブースでバッチリ記念撮影もして帰りました。

「子ども×救命救急」について考える
.jpg)
私自身、一度は救命講習を受講したことがあったので、今回は「おさらい」ぐらいの気持ちで参加していたのですが、初めて聞くことだったり(聞くのは2度目なのにきれいさっぱり忘れていたのかもしれません)、初めて知った実技のポイントなどもあり、救命講習って何度受けても良いんだなと痛感。
さらに今回は子ども達と一緒に参加したので、新しい気づきや視点をたくさん持つことができました。
子どもは応急手当てができる?

今回使用したのは幼児の人形でしたが、それでも小1女子の力では、胸の位置は全然下がらないし、乳児の胸骨圧迫も大人でも指が痛くなるほど意外と力を使うものでした。
一般的に、応急手当てができるようになるのは小学校高学年頃からとされているそうです。
救急現場で子どもが担える役割はある?


- 一緒に助けを呼ぶ(子どもの声で呼んだら、誰か来てくれるかも!)
- 迷子や車の危険がない場所なら、大人(お店の従業員の方など)を呼んでくる
- 胸骨圧迫の30回を一緒に数える(何度も繰り返していると数えるのが辛くなるので)
- プライバシー考慮のためのタオルや上着をかけてもらう
- AEDの場所を大人に教える(子どもの方が覚えているかも)
小学校高学年になれば、
- 倒れている人がいたら声をかける
- 119番に電話
- AEDを取りに行く
- 大人を呼んでくる
- 胸骨圧迫(パワーのある子なら!)
などもできると思います。
私の住む地域では、小学4年生以上の子どもに向けた「小学生のための救命講習」があり、命の大切さや、目の前で人が倒れた時に何ができるかを学べるそうです。
また、90分の救命入門コースも4年生から受講修了証をもらえます。

「子どもと参加」のリアルな感想
子連れOKとあったけれど、今回のようなスタイルの講習は、やっぱり子どもの面倒を見れる人が一緒に参加するべきだなと感じました。
夫は初めは真剣に話を聞きつつ、子どもたちの相手もしていたのですが、途中で謎の腹痛に襲われ退席。
今回は職員さんに子ども達の相手をしていただいて、私も2回目ということもあり、なんとか内容を理解できましたが、初めて受講するので一言も聞き逃したくない!という方には、子連れ参加はおすすめできません。
とはいえ、良いところももちろんありました。
解説や実技の指導の最中に、

と具体的に質問できます。こんなチャンスは滅多にないですよね。
また、子ども達にとっても、応急手当ての流れやAEDの使い方を見せることができるので、防災意識のタネを植えるのにはもってこいの機会です。
救命講習はさまざまな場所で開催されています。
修了証などがもらえるしっかりしたものでなくても、中には「親子救命講習」と銘打って子守スタッフを増員して、子どもが騒いでもOKな講習会を開催しているところも。
運よく見つけられたら、ぜひ参加してみてくださいね!

.jpg)

.jpg)
